私は今、不登校支援の様々な課題について深く考え、一つ一つ解決していこうと活動している。
今、活動しているプロジェクトは、「学校に行きたがらない子供とその親の、居場所を見つけた親子と見つけたい親子を繋ぐプロジェクト」。
これは全くの個人的プロジェクトである。しかし、社会的プロジェクトでもある。同じように課題を感じ、行動を始めている人たちや県があるからだ。私は今回このプロジェクトを始めるにあたって、福井県で活動されている方と直接お話しする機会を得た。https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukui/20250308/3050020108.html
そのかたはご自身も不登校の親という立場から、当事者に情報が届きにくい現状に課題を感じ、福井県に問題提示し協力を得る事ができた。現在、学校からの積極的不登校支援に繋げようと活動されている。
彼女の行動力と明るさ、バイタリティ、能力の高さにとても感銘を受けた。彼女のおかげで本格的に動き始めることができた。
先日、私はさいたま市の市議会議員の方に課題提示する機会をいただいた。
埼玉県には、不登校支援の課題について、当事者の声を届ける仕組みがない。
私の声を、行政に届けたい。その思いで、様々な方に協力して頂いている。
私の考える不登校支援の情報提供に関する課題
①子供が不登校(行き渋りも含む)になった時、不登校支援の情報が当事者・保護者・家庭にとても届きにくいこと。
②不登校支援に関する情報収集が親の努力に集約されていること。
③学校からの情報提供がほぼなく、情報提供力の学校間先生間格差があること。
③当事者目線の情報が少なく、悩む親は孤独感を抱えていること。
現状とアンケート結果
【R 5年度文部科学省調査結果より】
・不登校児童生徒数は11年連続で増加し、過去最多となっている。
・不登校児童生徒のうち90日以上欠席した者は55.0%であった。
⇨不登校というものが短期的に解決するものではなく、長期的なスパンで考えるべき出来事である事がわかる。長期化に伴い、本人はもちろん、支える家族の心理的、経済的負担も大きくなる。親子ともども安心できる居場所や相談施設の必要性がさらに増す。
・学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けた不登校児童生徒数は約21万2千人(前年度約18万5千人)で、不登校児童数に占める割合は61.2%(前年度61.8%)。
⇨この結果から注目すべきことは、相談受けていない割合が38.8%に上ること。R1年から、相談を受けている割合が減少している。(R1・70.4%、R2・65.7%、R3・63.7%、R4・61.8%)
この調査結果には驚いた。
考えられる理由として、担任が相談役、居場所の役割を任されているのではないだろうか?両親共働きで相談に行くのが難しいのだろうか?そもそもどこに相談すればいいのかわからない?現実を受け入れきれず、精神的に疲弊して外部に助けを求められない状況の人もいるのではないか?
・学校内外の機関などで専門的な相談指導を受けていない不登校児童生徒のうち、89.1%が担任などから週一回程度以上の継続的な相談指導を受けていた。
⇨この結果から、専門家でもない担任が相当の対応責任を課されている傾向があることが伺える。
【個人的に実施したアンケートや、各フリースクールのアンケートの調査結果より】
私は、個人的にアンケート調査を行った。方法として、知り合いの小学校の先生(さいたま市、東京都)に頼んで、不登校の親子にアンケート回答を頼んだ。また、知り合いの不登校の親にも協力をお願いした。その声を列挙したい。
《学校の初期対応について》
・不登校になった時、学校から不登校支援の情報がなく困った。
・学校から学校以外の居場所(フリースクール、放課後デイ、公的支援センターなど)につながる支援や情報提供が全くなかった。
・学校には、学校以外の居場所を伝えることに抵抗がある風土を感じた。
・再登校を目指す学校の先生からはフリースクールなどの積極的情報提供が難しい現状がある。
《居場所を探すにあたって》
・学校以外の居場所は人づてで自力で探したが、親子分離も不安がる子供であったため、施設見学することも難しく苦労した。
・フリースクールや放課後デイなどの居場所が自分の地域のどこに存在しているのかわからない。
・地域に支援機関を見つけても、そこが我が子に適しているのかわからない。我が子を受け入れてくれるのかわからない。
・子供が不登校になり、ひとりで解決するしかないと強い孤独感を感じた。
《あなたにとって必要な支援は何か》
・地域の不登校支援の情報が、学校から配布されたら読みたい。
・学校から情報提供してほしい。
・学習面や将来の不安が常にあり、『安心』がほしい。
・不登校経験者の生の声が聞けたり、不登校の先にどんな未来があるのかの情報がほしい。
・不登校親の会のような交流できる場の紹介があると助かる。
【埼玉県のホームページ、不登校支援のサイトの周知度の低さ】
埼玉県のホームページには、非常に一生懸命作成したと思われる不登校支援のサイトがある。この存在は、私は知らずにいた。もし、我が子が不登校になったばかりの時にこのサイトに出会えたら、大きく励まされた思う。サイト内の『民間活動団体・施設一覧表』では専門とする分野や対象者など、当事者が必要とする内容もうまく盛り込まれている。『不登校経験者の声』も載せてある。
これだけの有益な情報なのに、必要とする当事者に届きにくい現状。これこそが今解決しなくてはならない課題だと思うのだ。
アンケートに協力してくれた現小学校の先生2名に聞いてみたところ、彼らも存在を知らなかった。アンケート対象者も知らなかった。
【不登校当事者の声を届ける窓口がない】
情報提供の課題について、相談したいと思い、県庁に問い合わせたが、さいたま市に相談するように言われてしまった。さいたま市教育相談所に問い合わせ、窓口を聞いたが、はっきりとした回答が得られなかった。結果的にたらい回しとなり意見を伝える場に辿り着けなかった。当事者の声を聞かなければ、必要な支援は届けられないのではないかと思う。
解決に向けて提案
①県庁やさいたま市教育委員会などに、不登校当事者と意見交換できる窓口を作る。(福井県での実例:こども応援ディレクターの配置)
②行政と不登校の当事者が協力し、当事者目線の情報を載せたパンフレットを作成し、さいたま市内学校に配布する事で、学校間先生間の情報格差を是正し、情報提供の最低限ラインを確保する。
③孤独感を減らすには、経験者の生の声や仲間の声が有効である。行政と協力し、不登校経験者の生の声を、不登校で悩む親子へダイレクトに届けるシステムの構築し、常にオープンの状態にする。
最後に思うこと
今回の課題は増え続ける不登校児童を抱える家族にとって、全国的共通の問題である。福井県や徳島県で独自の方法で模索している様子が最近のニュースで取り上げられている。埼玉県も解決に向けて早急にプロジェクトを始動する必要があると思われる。
HINATA


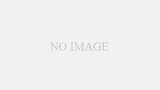
コメント